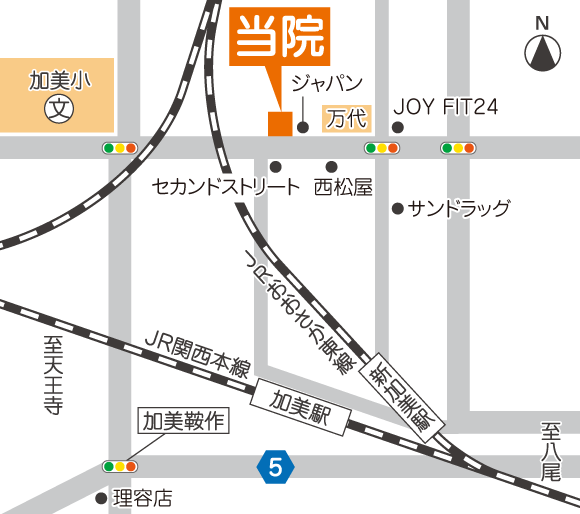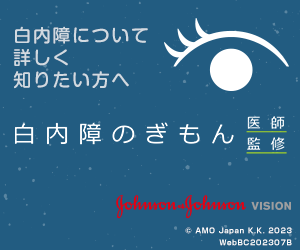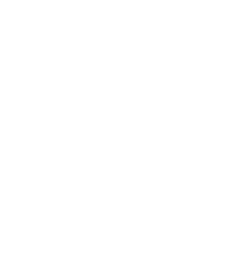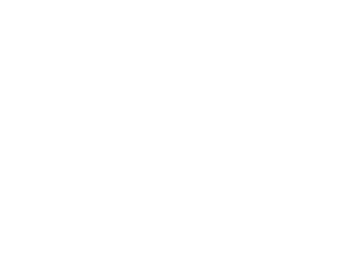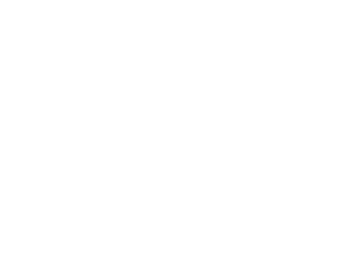診療内容
ドライアイ、白内障、緑内障などの一般診療、日帰り白内障手術、糖尿病網膜症等に対するレーザー治療、加齢黄斑変性等に対する硝子体注射、コンタクトレンズ取扱いをしています。
白内障
白内障について
白内障は、眼の中でレンズの役割を果たしている水晶体が年齢とともに濁ることで視力が低下する病気です。
水晶体は、目の中でカメラのレンズのようなはたらきをする組織で、外からの光を集めて網膜(カメラで言うフィルム)にピントを合わせるはたらきを持っています。
濁り方のタイプによって症状が違ってきますが、目のかすみと視力低下が代表的な症状です。
他の白内障の症状としては、次のような症状があります。
・目のかすみ(霧がかかったように目がかすむ)
・光をまぶしく感じる。
(夜間に対向車のヘッドライトがフラッシュを焚いたように見える)
・夜間に街灯の周りに輪がかかって見える。(光輪視)
・視力が低下する。
・急にめがねが合わなくなる。白内障が進行し水晶体が硬くなると度数が変化しメガネが毎年あわなくなるという症状が現れることもある。
このような症状があらわれたら、一度受診されることをすすめます。
白内障の治療
点眼薬による治療
白内障は老化現象ともいえますので、手術するほどでない場合には、点眼薬を用いて白内障の進行を遅らせるという方法をとります。(点眼で完全に進行を止めることはできません。)
手術による治療
白内障の症状が進み、日常生活に支障がある場合は手術をおこないます。
緑内障
緑内障について
ものを見るときに我々は、『網膜』という、カメラのフィルムのような役目をする組織に映像を映すことで見ています。
網膜には脳から伸びている、視神経という神経線維の束(たば)がつながっていて、網膜に映った映像を脳に伝達する役目を果たしています。緑内障はこの視神経の神経線維の数が減ってしまうことにより、網膜に映った映像を脳に伝達できなくなり、見えにくくなる病気です。進行すると失明することもあり、日本人の失明原因の第1位の病気です。
緑内障の症状
初期のうちは視野に部分的に見えないところが出現しますが、自覚症状はありません。
この時期の緑内障は、健康診断がきっかけで発見されたり、他の病気で眼科を受診した際にたまたま緑内障の検査を行って発見されることがあります。
もう少し進行すると、症状が出現しますが、典型的な症状はなく、眼が疲れるとか、老眼が進行した感じがするとか、様々な症状が実は緑内障の症状だったということがよくあります。視力が下がるほどの症状が出現している頃には緑内障は進行していることが多いです。
緑内障の検査
視野検査
見える範囲に見えていないところ(暗点)が無いかを調べます。
光干渉断層計(OCT)
視神経周囲の網膜の厚みを正確に測定することで、神経線維が欠損している場所と広がりを検査します。視野に異常が出る前のごく初期の緑内障(前視野緑内障)が発見できることもあります。
眼圧検査
眼の硬さを測ります。
隅角鏡検査
眼の中の水(房水)が排出される場所の構造を見て、どういうタイプの緑内障か検査します。
緑内障の治療
緑内障が進行するしくみは今のところ、完全に解明されていませんが、研究の結果、眼圧を下げると、緑内障の進行が抑えられる(すなわち視野が悪くなる早さが遅くなる)ことがわかっており、緑内障の治療は、点眼、手術等で眼圧を下げることで進行を抑制します。
平本眼科クリニックでは、治療前に測定した眼圧の値から、患者さんそれぞれの状態(緑内障のタイプ、視野の進行度、年齢等)を考慮し、目標とする眼圧値を設定し、その値を目標に眼圧を下げます。眼圧を下げる方法としては、以下のように点眼やレーザー治療、手術治療があります。
点眼による治療
眼圧を下げる効果のある目薬を点眼します。緑内障の点眼は作用機序から複数の種類のものがあり、それらを組み合わせて点眼します。最初は1種類から開始して、眼圧の下がり方が不十分な場合は2種類、3種類と追加します。
レーザー治療
点眼による眼圧の下がり方が不十分な場合に行います。眼の中を循環している房水の流出路に特殊なレーザーを当てて、房水の流れを良くすることで眼圧を下げます。当院で受けることができる治療です。
手術による治療
手術による治療につきましては下記ページをご覧ください。
当院での緑内障治療について
緑内障は治療によって視機能が改善することは無く、点眼も地道に続けていかないと、失明することも・・・と思わず暗い気持ちになってしまいそうな病気ですね。
当院では緑内障の治療を、『この目薬をさし続けないと、いつか失明します。3種類、4種類でも我慢してさしなさい。』というお話にするのではなく、『今のあなたの眼圧は目標の値をクリアしていますね。視野は目薬をしていてもゆっくり進行しますが、今の進行のペースであれば見えなくなるのは120歳を超える頃です。大丈夫ですね。』というお話に持って行くのを目指して治療方針を立てます。
目薬は3種類、4種類をさすと時間もかかるし、忘れるし・・とても大変な作業なので、当院では目薬が3種類以上になる場合は可能な限り、手術治療やレーザー治療を検討してその負担を減らすようにしています。
緑内障手術と聞くと怖いと感じる方もおられるかもしれませんが、最近は低侵襲緑内障手術(MIGS)という安全に行える手術方法もありますので、安心して受けて頂くことができます。
加齢黄斑変性
黄斑(おうはん)って何?
眼はカメラに良く似た構造になっていますが、カメラでいうフィルムに当たるのが『網膜』です。『黄斑』は網膜の中心部のことで、見ようとする視野の真ん中を担当しています。
視野の真ん中・・・ということは文字を読んだり、人の顔を見たりする時の真ん中に当たるので、黄斑に病気が起こった人は、文字を見ようとすると、ちょうどその文字の部分が見えない、見えにくい、あるいは人の顔の真ん中がゆがんだ変な形に見えるといった症状が起こります。
加齢黄斑変性とは・・
加齢黄斑変性は黄斑におこる病気です。
加齢により網膜に弱いところが生じ、そこに本来は発生しないはずの脈絡膜新生血管という悪い血管が網膜下に成長してくる病気です。新生血管が出血をおこしたり、水漏れをおこしたりすると、中心暗点(真ん中が暗く見える)や変視症(ものがゆがんで見える)を生じさせます。
病気が進行すると新生血管を治そうとする反応が起き、線維化する(病巣が固まる)ことにより不可逆的な(元に戻らない)視機能障害を残します。中には新生血管が大出血を起こして失明に至るケースもあります。
加齢黄斑変性の症状
初期の症状は中心暗点(視野の真ん中が暗く見える)や変視症(ものがゆがんで見える)です。片目をつぶって便箋などのまっすぐな線を見たときにゆがんで見える症状があるときは眼科を受診しましょう。病気が進行してくると中心暗点が強くなり、その範囲も広がります。
診断
加齢黄斑変性の診断はまず眼底検査を行い、出血や滲出(水漏れの所見)がみられた場合、蛍光眼底造影、光干渉断層計(OCT)等により診断します。
治療
現在では新生血管に対して効果のある薬を眼の中に注射する方法が主流となっています。注射により新生血管の勢いをしずめ、視力の維持を目的とします。当院でも可能な治療で、痛みもなく比較的安全な治療ですが、注射の効果は長続きしない場合が多く、定期的な注射が必要となります。
加齢黄斑変性にならないために・・
加齢黄斑変性の発症予防にビタミンやミネラル、ルテインが効果があることが証明されておりサプリメントでこれらの成分を摂取することは発症予防に有効とされています。
それ以外にも普段の食生活から緑黄色野菜を多く取る様にするのは有効でしょう。また喫煙は加齢黄斑変性のリスクを高めることもわかっており禁煙することをお勧めします。
加齢黄斑変性は今後増加すると言われており早期発見、早期治療が重要な病気です。少し変だなと思った際は眼科を受診するようにしましょう。
糖尿病網膜症
糖尿病が長く続くと・・・
糖尿病で血糖値が高い状態が続くと、からだの中の細い血管がまず傷害を受けます。
からだの中の細い血管・・というと眼の奥にある網膜(カメラのフィルムにあたる)を流れている網膜血管が代表です。糖尿病では、はじめに網膜血管が傷害を受けます。
初期の糖尿病網膜症
糖尿病によって網膜血管が傷害を受け続けると、血管の壁が破れて小さな出血(点状出血)をおこしたり、血管にこぶ(血管瘤)ができたりします。
また、血管の壁が弱くなると血液の中の水(血漿成分)が血管の外に漏れ出て網膜にたまったりします。このような時期を単純型網膜症と呼んでいます。
中期の網膜症(前増殖期糖尿病網膜症)
単純型糖尿病網膜症の状態でさらに血糖の高値が続くと、網膜血管が破れては修復し・・を繰り返すうちに、やがて閉塞(血管がつまる)します。
『網膜』はものを見るための神経でできた膜で、網膜はたくさんの酸素や栄養分を必要とします。網膜の血管がつまって網膜が酸素不足になると、それに対抗して網膜は眼内に血管を生やそうとする物質(VEGFなどと呼ばれる物質)を放出します。
その結果、網膜には『新生血管』という血管が成長するようになってきます。新しい血管が生えてきて血のめぐりが良くなって・・・となれば良いのですが、残念ながらそうはいきません。
新生血管は言ってみれば『出来そこない』の血管で正常な網膜血管のような機能を果たすことはありません。それどころか、新生血管はもろくて簡単に破れてしまい、出血の原因になったり、次に述べます増殖膜という悪い膜を作ったり、血管新生緑内障という恐ろしい緑内障の原因になったりします。
末期の糖尿病網膜症(増殖糖尿病網膜症)
網膜に新生血管が多発してくると糖尿病網膜症はいよいよ重症の段階に入ります。
新生血管が破れることで眼の中に出血(硝子体出血)を起こしたり、新生血管を取り囲むように増殖膜という膜を形成したりするのがこの時期です。
増殖膜は網膜に強く癒着している(くっついている)ので、増殖膜が成長してくると癒着しているところで網膜を引っ張る様になってきます。網膜を引っ張る力が強くなると、網膜は眼の奥からはがれるようになります(牽引性網膜剥離)。
新生血管の勢いが強いケースでは、眼の中の水の排水溝を新生血管がふさいでしまい、水の排出がうまくいかなくなる結果、眼圧(眼の硬さのこと)が上昇し、視神経を傷害することで悪性の緑内障となってしまうこともあります(血管新生緑内障)。
このように牽引性網膜剥離や血管新生緑内障は最悪の場合、失明につながる併発症で手術を含めた治療が必要となります。
糖尿病網膜症の症状
初期の単純型網膜症の時期は自覚症状に乏しいことも多く、自分では気づかないうちに進行していたということもあります。
中期以降に新生血管から出血したり、網膜浮腫が中心部に及んだり(黄斑浮腫)すると、飛蚊症(黒いものが飛んで見える)や視力低下を自覚するようになってきます。
糖尿病の患者さんの中には眼の症状がないからといって眼科受診を怠っている方がおられますが、自分では気づかないうちに糖尿病網膜症が重症となっていることがあります。
血糖コントロールが良くても糖尿病のある方は定期的な眼科受診が不可欠です。健康診断の眼底写真では糖尿病網膜症が見過ごされることが多く、眼科での定期的な眼底検査が必要です。
糖尿病網膜症の治療
単純型の時期は血糖コントロールの改善により眼も改善することがあります。
この時期は血糖コントロールが網膜症の治療にもなります。前増殖期以降まで進行すると血糖コントロールだけでは糖尿病網膜症の進行は止めることができません。
この時期になると、毛細血管が閉塞した領域の網膜に対してレーザー治療が必要になります。硝子体出血や牽引性網膜剥離に対しては硝子体手術(眼の中の操作をする手術)が必要になることもあります。最近では糖尿病網膜症による黄斑浮腫(網膜のむくみ)の治療に硝子体注射(眼の中に注射をする)も行われています。
糖尿病の患者数は今後も増加すると言われており、糖尿病による失明の予防のために眼科受診を定期的にして網膜症の早期発見に心がけましょう。